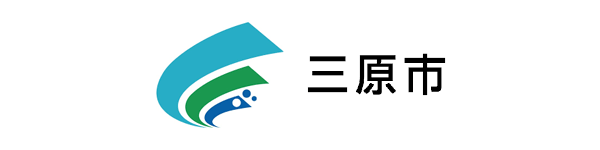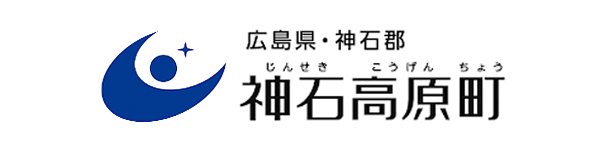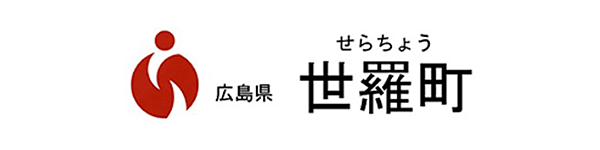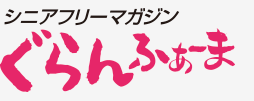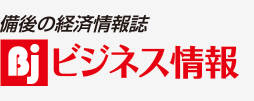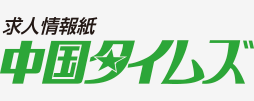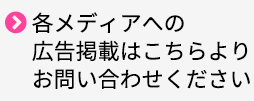- 歴史散歩
入封400年記念シリーズ(6)福山における野々口立圃の足跡
明王院
福山 更新:2021年09月09日
No.313
戦国武将は戦に明け暮れただけでなく文芸に通じた教養人でした。福山藩初代藩主水野勝成も連歌や和歌に通じ、俳諧の心得がありました。勝成により築城当初から福山には文芸を受け入れることのできる素養があったのです。
京都の俳諧の祖といわれた立圃は、2代藩主である勝俊の御伽衆として1651(慶安4)年に福山を訪れます。和歌や連歌、書画、俳画に長じた立圃の作品はユーモアがあります。福山にも多くの弟子や同好者がおり、藩士や町人衆にも俳諧や和歌が広まりました。
福山滞在中の立圃は水野勝成の追悼記や、勝俊が江戸藩邸で亡くなったことを残した「信解院殿御臨終記」を記しました。また草戸を中心にした紀行文「福山近在名所記」は著名です。
その文中の「ほとほとと たゝけ草戸の 子規」の句は、地名を草土から草戸に変更する要因となりました。
草戸の明王院は水野家の祈願寺で立圃とも密接な関係がありました。立圃直筆の文書などが伝わっており、市重要文化財に指定されています。
現在も福山では俳諧をたしなむ人が多く、市民大学や公民館でも教室が盛んで俳句人口は増えています。

タグ: 福山
INFORMATION基本情報
| 名称 | 明王院 |
|---|---|
| 住所 | 広島県福山市草戸町1473 |
※最新の情報とは異なる場合があります。
ご了承ください。
同じカテゴリーの記事
-

未来に歩み出す姿 阿部正弘の像
-

地下に眠る築城時の遺跡 入川(いりかわ)
-

鉄壁の防御の構え 福山城天守北側鉄板張り
-

築城時の天守を支えた 福山城旧天守礎石
-

福山城東側の威容を語る 東坂三階櫓(やぐら)跡と多聞櫓跡
-

瀬戸内の水運5 中・近世山陽道
-

今も水を湛える 黄金水
-

築城当時から残る本丸の正門 福山城筋鉄御門
-

瀬戸内の水運4 市史跡イコーカ山古墳
-

火災から文化財を守る 文化財防火デー
-

今も時を告げる 福山城鐘櫓
-

福山城の歴史を見守り続けた 城内の樹木
-

瀬戸内の水運3 御領遺跡
-

瀬戸内の水運2 津之郷谷
-

二度の金属供出を免れた「明圓寺銅鐘」
-

瀬戸内の水運1 松永湾を見守る首長の墓
-

葛原家と縁のある 福寿会館
-

近世水道の分水界 本庄村二股
-

福山城入川の存在を示す 名もなき橋
-

かつて海であったことを物語る蛙岩
-

邪鬼を払う 福山城の鬼門守護
-

今年の干支牛を祀る 大山社
-

夜空を照らす豊穣への祈り お月さん
-

疫神・悪霊を防ぐ 塞神